

| HOME | 会社概要 | 質問にお答えします | 長期優良住宅の断熱 |
| 木造住宅の断熱 | マンションの断熱 | 通気層について | 地震について | 火災について |
| 1) 釘の経年劣化について 2)発泡プラスチックはシロアリの被害があります |
1)【地震などの天災について】
| 阪神・淡路大震災の時も中越地震の時も被害の大きかった家屋の大部分は築年数の古い建物です、200年という年を考えれば一回は大きな地震に遭遇する確率が高いと言えます。 このことから200年住宅についてもっとも考えなければならないのは地震によって崩落しない建物の強さと脱落しない外壁、そして釘の経年劣化を防ぐ工法です。。 |
立地条件の負の部分について設計士や工務店と時間をかけて検討しなければ200年住宅は建てられません、断熱の方法を変えるだけでは200年住宅は作れません。 |
2)【阪神・淡路大震災】
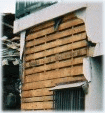 |
左官組合の調査によれば阪神淡路大震災の時の外壁モルタルの落下の原因は、ラス網をとめていた又釘(タッカー針)が錆びて支持力が無くなったのが原因と報告されています。 中越地震の時のラスシートモルタルの落下はCチャンにとめていたビスの腐食が原因と報告されています。 200年住宅の外壁を止めるもの(タッカー針等)はステンレス製にするべきです。 |
3)【木造住宅の断熱の構造について】
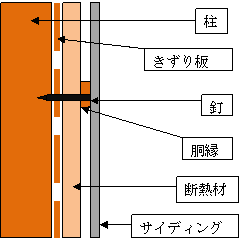 |
図は一般的な外張り断熱工法です(図では横胴縁ですが実際は縦胴縁にして通気層にしていることが多い)、構造的に弱い断熱材を間に入れて、長い釘かビスによる点接着で外壁を保持する形をとっています。 宮大工の棟梁の話を聞いた時、「宮大工は釘を使わないというのは嘘で、釘を使いますが耐久性の必要なところは釘を使わず木組みにします、鉄と木は相性が悪いのです」と言っていました。 数十年たって釘やビスが錆びれば(経年劣化)地震に弱い構造になります。 50年〜60年位の耐用年数を目標にした住宅ならば問題が起きることはありませんが、200年の耐用年数を求めるならばその間に大地震に遭遇する可能性は大きくなります、また繰り返される小さな地震で釘やビスは緩みやすくなります、木造の200年住宅には充填断熱の方が良いと言えます。 |
|
最近の壁構造は、強度を釘に頼っているところが大きいので釘の劣化を無視するわけにはいきません。 左の表は保坂貴司著 (株)エクスナレッジ発行の「釘が危ない」と言う本に載っていた釘の劣化度を示すデータです。 この資料によれば劣化度3までは強度上は問題ないのですが劣化度4になると強度上大きな問題があることが分かります。 釘は何年ぐらい持つのか?「釘が危ない」と言う本の中で保坂貴司先生が調査した結果の文章が載っているので転載させていただきます。 |
| 《私が調査した事例によると、築25年の外壁モルタルの建物で地盤より高さ1.0m以内に使用されているN32釘の約5割が劣化度4、築40年の外壁モルタル壁の建物で地盤より1.0m以内に使用されているN32釘の約60%が劣化度4でした。〜中略〜このように1階床周辺の釘は劣化が進んでいたのですが、2階床周辺で使われている釘はほとんど劣化は見られませんでした。いくつかの事例だけで結論を出すのは早計ですが、木材の含水率が高い部分に使用されている釘の劣化は大きいといえそうです。》 |
釘の劣化の原因(1)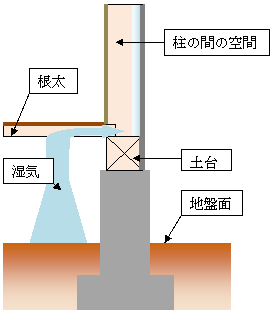 |
保坂先生の調査では釘の劣化の原因は、木材の含水率にあり含水率が高くなると劣化は進むようです。 一階の床付近の木材の含水率が高い原因としては、床下の地面の湿気や布基礎の通気口から入り込んだ湿気が、根太の隙間などから壁の中に入り込み(当時の壁は中空)、壁の中が多湿になりその湿気を木材が吸収して木材の含水率が高くなったのです。 この現象は地盤面に近いところから空気が壁の中に入り込む構造ではどのような工法でも起こりうる現象です。 劣化とか腐食というのは時間がたてば広がる物なのですが、釘の劣化の場合は地盤面から1m位の所の釘だけが集中して劣化の程度が進むようです。 保坂貴司著 (株)エクスナレッジ発行の「釘が危ない」と言う本はこれから家を建てようとする方には必ず読んでほしい本です、正しい釘が使われない理由や建築業界の受注システムなど、参考になる事が多々あります。 |
|
||||||||||||
| 上の表は腐巧菌などのカビの発生条件と増殖条件を示したものです。 1978年「北方圏寒地住宅視察団」が訪れたストックフォルムなどは年間を通じてカビの増殖条件に当てはまる日はほとんどありませんが、東京など温暖な地域では年間60日以上カビの増殖条件になることがある日があります、北海道のように夏でもさわやかで結露と言えば冬の室内の表面結露という地方では、より気候条件の厳しい地方を参考にするのは正しいことであり、またそうすべきです。 しかしながら、高温多湿の夏がある東京など温暖な地方では異なった気象条件の国の湿気の処理方法を真似るよりも、日本古来の蔵造りの湿気の処理方法(壁内に通気層をつくらず湿気が壁の両面に抜けていく工法)が建物を長持ちさせる工法です。 腐巧菌は常在菌(空気のあるところにはどこにでもいる菌)ですから、蔵造りの壁のように通気層だけでなく空気層も無い壁構造の方が高温多湿の地方には合っています。 木材は含水率が25%になると劣化が始まり、35%になると腐巧菌が発生します、内部結露はもちろん雨水の滲入も防がなければなりません。 |
| スタイロフォームの白アリ被害 | コンクリートの白アリ被害 | スタイロフォームの蟻道被害 |
 |
 |
 |
| シロアリについての詳しいことは社団法人日本シロアリ対策協会のHPから調べてもらうのが一番良いのですが、高気密・高断熱住宅との関連で知っておいていただきたいことを挙げてみます。
|
「床下が危ない」(株式会社エクスナレッジ発行 神谷忠弘著)より シロアリについての迷信俗論
|
| このページのトップへ戻る |